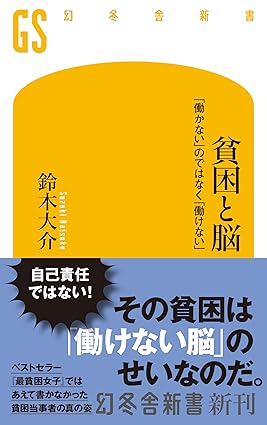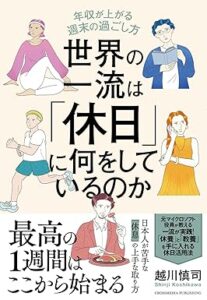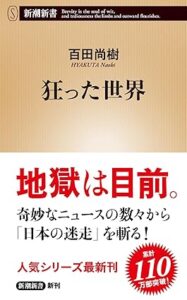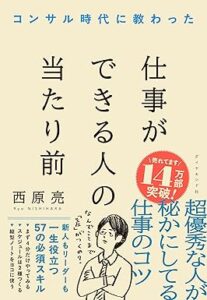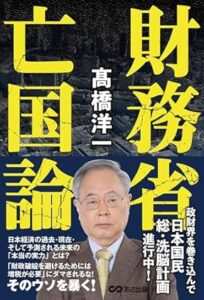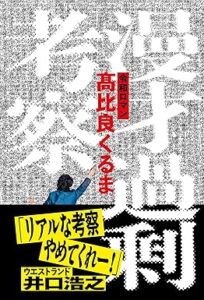| 書籍タイトル | 貧困と脳 「働かない」のではなく「働けない」 |
| 著者 | 鈴木大介 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
| 発売日 | 2024年11月27日 |
どんな人におすすめの本か
- 貧困問題に関心がある方
- 脳科学に関心がある方
- 社会問題を多角的に捉えたい方
本の要約
約束を破る、遅刻する、だらしない。長年取材してきた貧困の当事者には、共通する特徴があった。世間はそれを「サボり」「甘え」と非難します。しかし著者は、病気で「高次脳機能障害」になり、どんなに頑張ってもやるべきことが思うようにできないという「生き地獄」を味わいました。当事者になってはじめてわかった。貧困による脳機能の低下です。
最新の研究では、貧困や幼少期の逆境体験が、脳の発達に悪影響を与えることが明らかになっています。例えば、ストレスホルモンの過剰分泌は、脳の前頭前野の機能を低下させ、衝動性や判断力の低下を引き起こす可能性があります。また、栄養不足や睡眠不足も、脳の機能を低下させる要因となります。貧困状態にある人々は、このような脳機能の低下により、長期的な計画を立てることや、感情をコントロールすることが困難になりがちです。
その結果、目の前の誘惑に負けやすくなったり、将来よりも今を優先するようになったりすることがあります。これらは、怠惰や自己責任といった言葉で片付けられることが多いですが、脳科学的には、貧困による脳機能の低下が原因である可能性も否定できません。本書は、貧困問題を脳科学の視点から捉え直し、新たな解決策を提示する一冊です。
第1章:貧困と脳科学
この章では、貧困が脳に与える影響について、脳科学の研究結果を交えながら解説します。具体的には、貧困によるストレスや栄養不足が、脳の構造や機能にどのような影響を与えるのか、最新の研究データを基に詳しく解説します。また、貧困状態にある人々が抱えやすい認知機能の低下や、感情制御の困難さについても、脳科学的な視点から解説します。貧困が単なる経済的な問題ではなく、脳機能にも影響を与える深刻な問題であることを、読者は理解を深めることができるでしょう。
第2章:ストレスと脳
この章では、貧困によるストレスが、脳の機能にどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。貧困状態にある人々は、常に経済的な不安や将来への不安にさらされています。このような慢性的なストレスは、脳の扁桃体の活動を過剰にし、前頭前野の機能を低下させることが知られています。その結果、衝動的な行動や、長期的な計画を立てることが困難になるのです。また、ストレスホルモンの過剰分泌は、脳の海馬の神経細胞を減少させ、記憶力や学習能力の低下を引き起こす可能性も指摘されています。
第3章:栄養と脳
この章では、貧困による栄養不足が、脳の発達や機能にどのような影響を与えるのかを解説します。脳は、適切な栄養素がなければ正常に機能しません。特に、幼少期の栄養不足は、脳の発達に深刻な影響を与える可能性があります。貧困状態にある人々は、栄養価の高い食品を十分に摂取できないことが多く、その結果、脳の神経伝達物質のバランスが崩れたり、脳細胞の成長が阻害されたりする可能性があります。また、鉄分やビタミンB群などの不足は、集中力や記憶力の低下を引き起こすことが知られています。
第4章:睡眠と脳
この章では、貧困による睡眠不足が、脳の機能にどのような影響を与えるのかを解説します。睡眠は、脳の休息と回復に不可欠な役割を果たします。しかし、貧困状態にある人々は、騒音や劣悪な住環境、精神的なストレスなどにより、質の高い睡眠を得ることが困難な場合があります。睡眠不足は、脳の認知機能や感情制御機能を低下させ、日中のパフォーマンスに悪影響を与えます。また、長期的な睡眠不足は、脳の構造にも変化をもたらす可能性が指摘されており、注意機能や記憶機能の低下を引き起こす可能性があります。
第5章:貧困脱出への道
この章では、貧困による脳機能の低下を克服し、貧困から脱出するための具体的な方法を提案します。脳科学の研究成果に基づき、貧困状態にある人々が抱える脳機能の課題を克服するための、効果的な支援策を紹介します。例えば、認知行動療法やマインドフルネスなどの心理療法は、ストレスや衝動性をコントロールするのに役立つ可能性があります。また、栄養バランスの取れた食事や、質の高い睡眠を確保するための具体的な方法も提案します。さらに、社会的な支援制度や、教育機会の提供など、貧困の連鎖を断ち切るための包括的なアプローチについても考察します。
全体を通して
「貧困と脳 「働かない」のではなく「働けない」」は、貧困問題を脳科学の視点から捉え直すことで、新たな解決策を提示する一冊です。本書は、貧困状態にある人々が、決して怠惰や自己責任でそうなっているのではなく、脳機能の低下により、そのような状況に陥りやすいことを示唆しています。
このことを理解することは、貧困問題に対する偏見をなくし、より効果的な支援策を検討する上で非常に重要です。本書は、貧困問題に関心があるすべての人に、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
読者レビューを一部紹介
Amazonレビュー
- ★★★★★ 貧困に対する見方が大きく変わりました。
- ★★★★★ 脳科学の視点から貧困問題を解説していて、非常に興味深かったです。
- ★★★★☆ 貧困問題の解決策を考える上で、参考になる情報が満載でした。
- ★★★★★ 社会問題を多角的に捉えることの重要性を学びました。
- ★★★★☆ 貧困問題に関心があるすべての人に読んでほしい一冊です。
楽天ブックスレビュー
- ★★★★★ 貧困は自己責任という言葉で片付けられないことを痛感しました。
- ★★★★★ 脳科学の知識がなくても、分かりやすく解説されていました。
- ★★★★☆ 貧困問題に対する偏見をなくすきっかけになりました。
- ★★★★★ 貧困問題の解決に向けて、私たちにできることを
- ★★★★☆ 非常に読み応えのある一冊でした。
まとめ
「貧困と脳 「働かない」のではなく「働けない」」は、貧困問題を脳科学の視点から捉え直し、新たな解決策を提示する一冊です。貧困問題に関心があるすべての人に、ぜひ読んでいただきたい一冊です。